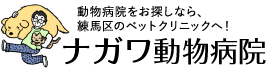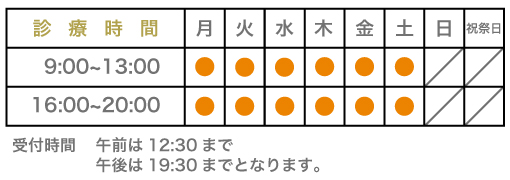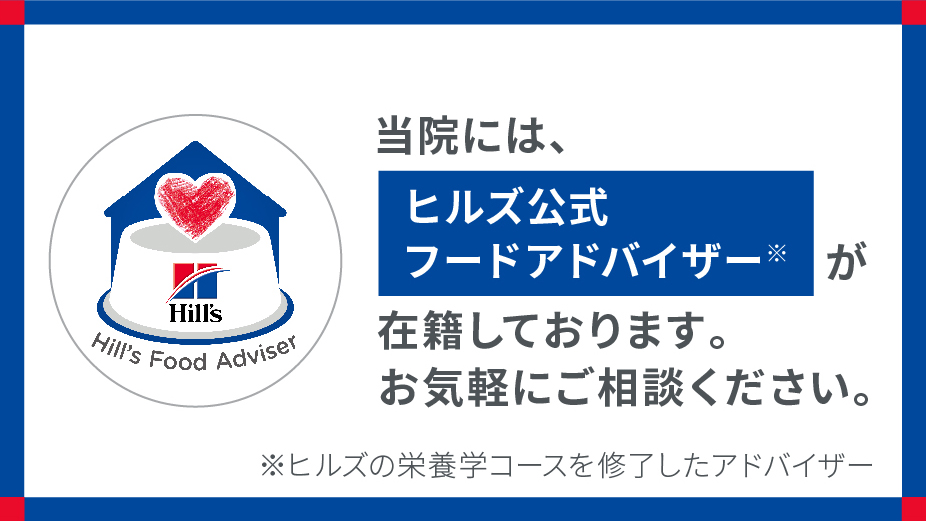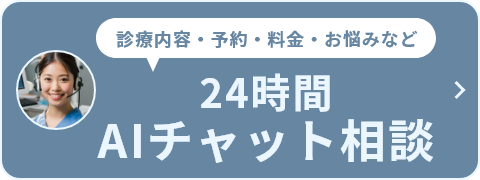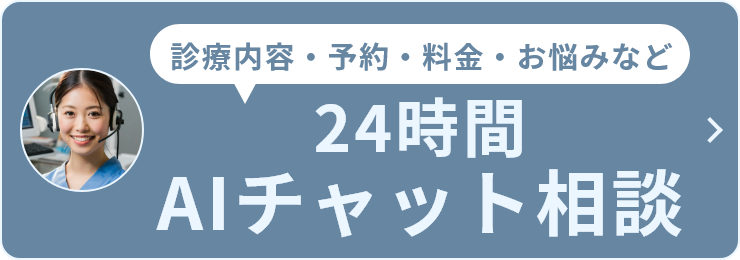犬の白内障|目薬で治る?進行を止める?手術が必要な症状と治療を解説
犬の白内障について調べると「目薬で治るの?」「進行を止められる?」といった情報を目にすることが多いかもしれません。結論からお伝えすると、白内障を目薬だけで元の状態に戻すことは、基本的に難しいと考えられています。
点眼治療の主な目的は、白内障そのものを治すことではなく、進行をゆるやかにしたり、炎症などの合併症を抑えたりすることです。一方で、白内障の進行度や原因、全身状態によっては、手術を検討するケースもあります。大切なのは「目薬か手術か」を先に決めることではなく、今どの段階にあるのかを正しく知り、その子に合った治療方針を選ぶことです。
今回は、犬の白内障について、症状の見分け方から検査、治療の考え方について詳しく解説します。
■目次
1.すぐ受診したいサイン|こんな変化は見逃さないで
2.犬の白内障とは|水晶体が濁ることで起こる変化
3.核硬化症との違い|「白っぽい=白内障」ではありません
4.犬の白内障の原因|特に注意が必要なのは糖尿病性
5.動物病院での検査・診断の流れ
6.治療方法|点眼(目薬)と手術、それぞれでできること・できないこと
7.ご家庭でできること|日常生活での配慮
8.よくある質問(FAQ)
9.まとめ
すぐ受診したいサイン|こんな変化は見逃さないで
白内障はゆっくり進行することも多い一方で、状態によっては短期間で悪化するケースもあります。次のような変化がみられる場合は、早めの受診をおすすめします。
・目の中(水晶体)が急に白っぽくなった
・物や壁にぶつかる、段差を怖がるようになった
・目が充血している、痛そうにしている
・目やにが増えた
特に糖尿病を持っている犬では、白内障が急速に進行することがあるため、見た目の変化が少ないように感じても注意が必要です。
糖尿病について詳しく知りたい方はこちら
犬の白内障とは|水晶体が濁ることで起こる変化
犬の目は、外側から角膜・水晶体・網膜という構造でできています。このうち水晶体は、カメラのレンズのように光を集め、網膜に像を結ぶ重要な役割を担っています。
白内障とは、この水晶体が濁ってしまう病気です。濁りが進むにつれて光がうまく届かなくなり、視力が低下します。
白内障は進行の程度によって、一般的に以下の段階に分けられます。
・初発白内障
・未熟白内障
・成熟白内障
・過熟白内障
初期の段階では視力低下に気づきにくいこともありますが、進行すると日常生活に支障が出るだけでなく、目の中で炎症(ぶどう膜炎)を起こすリスクも高まります。
核硬化症との違い|「白っぽい=白内障」ではありません
高齢の犬で目が白っぽく見える場合、白内障ではなく「核硬化症」という変化の可能性もあります。
核硬化症は、水晶体が加齢によって硬くなる現象で、見た目は白内障に似ていても、視力への影響はほとんどないとされています。治療が不要なケースも多く、白内障とは対応が異なります。
見た目だけでの判断は難しいため「白く見える=白内障」と決めつけず、必ず検査で見極めることが大切です。
犬の白内障の原因|特に注意が必要なのは糖尿病性
犬の白内障には、さまざまな原因があります。代表的なものとして、次のような要因が挙げられます。
・遺伝的要因
・加齢
・糖尿病
・ぶどう膜炎
・外傷
なかでも糖尿病性白内障は進行が非常に速いことが知られており、数日〜数週間で急激に悪化するケースもあります。糖尿病を持つ犬では、目の色の変化や見え方の変化に早めに気づき、できるだけ早く受診することが大切です。
また、ヨークシャー・テリアやボストン・テリアなどのテリア種は、遺伝的に白内障を発症しやすい傾向があるとされています。ただし、どの犬種でも白内障を発症する可能性があるため、犬種に関わらず、日頃から目の様子を観察しておくことが重要です。
動物病院での検査・診断の流れ
白内障が疑われる場合、動物病院では目の状態と全身の健康状態をあわせて確認しながら、段階的に検査を進めます。
▼目の状態を詳しく確認
専用の器具を使って、目の表面や内部の様子を観察し、白内障の進行度や炎症の有無を確認します。あわせて眼圧を測定し、緑内障などの合併症が起きていないかもチェックします。
▼必要に応じて全身チェック
糖尿病などの全身疾患が疑われる場合には、血液検査などを行い、体の状態を確認します。目だけでなく全身の情報を把握することで、治療方針をより安全に判断できます。
▼手術を検討する場合の追加評価
手術が選択肢に入る場合は、麻酔の安全性や網膜の状態などを評価し、その子にとって手術が適切かどうかを慎重に判断します。
検査内容は、白内障の進行度や体調によって異なります。気になる変化があれば、まずはお気軽にご相談ください。
治療方法|点眼(目薬)と手術、それぞれでできること・できないこと
犬の白内障治療には、大きく分けて「点眼(目薬)による治療」と「手術」の2つの選択肢があります。ただし、どちらが適しているかは、白内障の進行段階や原因、愛犬の年齢や持病などによって大きく異なります。
ここでは、それぞれの治療で期待できること・注意点を整理してご紹介します。
<点眼(目薬)治療でできること・限界>
白内障に対する点眼治療の主な目的は、白内障そのものを元に戻すことではなく、進行をゆるやかにしたり、炎症などの合併症を抑えたりすることです。
初期〜比較的早い段階の白内障では、進行抑制が期待できるケースもあります。一方で、すでに濁りが強く進行している場合には、点眼だけでは十分な効果が得られないことも少なくありません。そのため点眼治療は、効果の出方や進行の様子を定期的に確認しながら、治療方針を調整していくことが大切になります。
一般的には、加齢性白内障の進行抑制が期待される成分や、抗酸化作用が報告されている成分などが使用されます。当院でも、こうした考え方を踏まえ、状態に応じてライトクリーンやD-Smileなどの点眼薬を使用することがあります。ただし、いずれの点眼薬も「白内障を治す薬」ではなく、効果には個体差や限界がある点を理解しておくことが大切です。
<手術(白内障手術)を検討するケース>
白内障手術は、白く濁った水晶体を取り除き、人工レンズを挿入する外科治療です。犬の場合、人の白内障手術のように「視力を大きく回復させる」ことを目的とするのではなく、炎症や緑内障などの合併症を防ぐ意味合いが大きい点が特徴です。
例えば、次のような場合には、手術が選択肢として検討されることがあります。
・視力低下が進み、物にぶつかる、怖がって歩かなくなるなど、生活に支障が出ている
・白内障に伴う炎症や緑内障のリスクが高い
・水晶体脱臼が起こっている、または起こる可能性が高い
一方で、糖尿病性白内障、高齢(おおよそ15〜16歳以上)、重い心臓病などの持病がある場合、両目とも重度に進行している場合などでは、手術が適さないケースもあります。
手術には麻酔リスクや術後のケア、通院管理も必要になるため、必ずメリットとデメリットを比較しながら、慎重に判断していきます。
眼科手術について詳しく知りたい方はこちら
ご家庭でできること|日常生活での配慮
白内障が進行すると、これまで当たり前にできていた動きが少しずつ難しくなり、愛犬が不安を感じやすくなります。安心して過ごせるよう、日常生活の工夫や、治療の継続、小さな変化への気づきが大切です。
<生活環境の工夫>
視力が低下してくると、段差や物の位置が分かりづらくなり、思わぬケガにつながることがあります。次のような工夫を取り入れることで、日常の負担を減らすことにつながります。
・家具の配置をできるだけ変えない
・床の小物やコードを整理する
・段差には滑り止めマットを敷く
・夜間は足元灯などで明るさを補う
<点眼治療を続ける際の注意点>
点眼治療は、自己判断で中止したり回数や種類を変えたりせず、獣医師の指示に沿って続けることが重要です。
また、症状が落ち着いて見えても、目の中では変化が進んでいることもあります。充血や目やにが増える、痛がる様子が見られるなど、いつもと違う変化があれば早めにご相談ください。点眼が難しい場合も、方法や対応を一緒に考えていきましょう。
<日々の変化を見逃さない>
歩くスピードが遅くなった、段差を怖がる、物を見失うことが増えたなどの変化は、治療方針を見直すサインになることがあります。ご家庭での見守りと定期的なチェックを組み合わせながら、愛犬が安心して過ごせる環境を整えていきましょう。
よくある質問(FAQ)
白内障について、飼い主様から特に多く寄せられるご質問をまとめました。
Q:白内障は目薬だけで治りますか?
白内障を元に戻すことは、目薬だけでは難しいと考えられています。主な目的は進行をゆるやかにすることや、炎症などのトラブルを抑えることです。状態によって効果の出方は異なります。
Q.…

犬の胃捻転、手術後の生存率は?胃固定術で防げる再発リスク
大型犬が、食後に突然そわそわし始め、おなかが張ってくる――
そんな様子が見られたとき、一刻の猶予も許されない病気が「胃捻転(GDV)」です。
胃捻転は進行が非常に早く、発症から数時間で命に関わる状態に陥ることもあります。しかし一方で、早期に発見し、適切な外科治療を行うことができれば、回復して元の生活に戻れる可能性がある病気でもあります。
今回は、犬の胃捻転がなぜ一刻を争う緊急性の高い病気なのかをはじめ、飼い主様が気づきやすい初期のサイン、実際に行われる手術の内容や術後の生存率、そして再発を防ぐために重要となる胃固定術について、詳しく解説します。
■目次
1.犬の胃捻転(GDV)とは|なぜ「様子見」ができないのか
2.診断と初期対応|レントゲンと緊急整復手術
3.胃捻転の手術と生存率|“治る”可能性はある?
4.胃固定術とは|再発率を大きく下げる重要な処置
5.まとめ|早期判断と胃固定術が、命とその後の生活を守る
犬の胃捻転(GDV)とは|なぜ「様子見」ができないのか
胃捻転(GDV:胃拡張捻転症候群)は、胃がガスや内容物で膨らみ、ねじれてしまうことで発症します。この病気で特に重要なのは「命に関わること」と「短時間で急激に悪化すること」です。
胃がねじれることで、体の中では次のような深刻な変化が連鎖的に起こります。
・血流障害
胃がねじれる際に太い血管も巻き込まれ、全身の血流が低下します。
・ショック状態
血流障害によってショックを引き起こし、体温や血圧の低下、呼吸の乱れ、心拍数の増加などがみられます。進行すると命に関わる危険な状態です。
・胃壁の壊死・腹膜炎
胃の血流が滞ったままになると胃壁が壊死し、さらに進行すると胃に穴が開いて腹膜炎を引き起こすこともあります。
こうした変化は一気に進行するため、数時間前まで元気だった犬が、短時間で命の危険にさらされることがあります。これが胃捻転の最大の怖さとも言えます。
<起こりやすいタイミング・犬の特徴>
胃捻転は、次のような条件で起こりやすいことが知られています。
・食後・大量の飲水後
一気食い・一気飲みのあとに動き回る習慣がある場合は注意が必要です。
・大型犬・胸の深い体型の犬
グレート・デーンなど、胸が深い大型犬種で発症しやすい傾向があります。
「少し休めば落ち着くかも」と様子を見ている間に、全身状態が急激に悪化してしまうことがあります。胃捻転は“経過観察”ができない病気であり、早期発見と迅速な対応が命を左右します。
診断と初期対応|レントゲンと緊急整復手術
飼い主様が気づきやすいサインとして、次のような症状が挙げられます。
・急に吐く
・吐こうとしているのに吐けない
・食欲が急になくなる
・おなかが張る・膨れる(特に胃のあたり)
これらの症状が見られた場合、迷わず動物病院を受診することが重要です。
<診断と初期対応の流れ>
胃捻転が疑われる場合、レントゲン検査で胃の位置やねじれを確認します。診断がついた時点で、すでに緊急対応が必要な状態です。
まず行われるのが、
・食道から管を入れる
・皮膚の上から針を刺す
といった方法による胃内ガスの減圧処置です。
これにより胃の膨張を抑え、ショック症状を一時的に安定させます。同時に輸液治療を行い、血圧低下や循環不全を防ぎます。
胃捻転の手術と生存率|“治る”可能性はある?
胃捻転の根本治療は、ねじれた胃を元の位置に戻す「整復手術」です。
手術ではおなかを開けて、胃を正しい位置に戻しながら、胃壁に壊死がないか、切除が必要な部分がないかを確認します。状態によっては、壊死した胃の一部を切除することもあります。
発症初期で状態が軽く、減圧処置のみでねじれが解除されるケースもまれにありますが、多くの場合は手術が必要になります。
<生存率に影響するポイント>
「胃捻転=助からない病気」という印象を持たれることもありますが、早期に手術が行えた場合、多くの犬が回復しています。
一方で、以下の条件が重なると予後に影響します。
・発症から来院までに時間がかかっている
・胃壁に壊死が起きている
・重度のショック状態に陥っている
そのため、早期発見・早期治療が何より重要です。
胃固定術とは|再発率を大きく下げる重要な処置
胃捻転の手術では、整復手術とあわせて「胃固定術」を行うことが非常に重要です。
<胃固定術の目的>
胃固定術とは、胃の一部を腹壁に縫い付け、再びねじれないように固定する処置です。
整復手術のみでは再発リスクが高く、ある報告では次のような大きな差が示されています。
・減圧処置+整復手術のみ:再発率…

犬・猫の肛門嚢摘出術|肛門腺の腫れ・痛み・悪臭が続くときの治療法
犬や猫と暮らしていると、肛門腺(肛門嚢)のニオイや汚れが気になった経験がある方は多いのではないかと思います。
実は肛門腺のトラブルは“ニオイ”だけの問題ではなく、炎症・感染・破裂・腫瘍など、放置すると深刻な状態に進行することもあります。早い段階で気づき、適切な治療につなげることで、おしりの不快感や痛みから解放し、より快適に過ごせるようになります。
今回は、肛門腺のトラブルを根本的に改善する治療法として「肛門嚢摘出術」を中心に、当院での考え方をご紹介します。
■目次
1.肛門腺の役割と犬・猫で起きやすいトラブル
2.保存療法で改善するケース・改善しないケース
3.肛門嚢摘出術とは?メリット・リスクについて
4.まとめ
肛門腺の役割と犬・猫で起きやすいトラブル
まずは、肛門腺(肛門嚢)がどんな働きをしているのかを簡単にご説明します。
肛門腺は、強いニオイを持つ分泌物をつくり、それを肛門嚢(肛門の左右4時・8時方向にある袋状の器官)にためる仕組みになっています。健康な状態であれば、この分泌物は便と一緒に自然に排出されるため、特別なケアは必要ありません。
しかし、分泌物がうまく排出できない状態が続くと、次のようなトラブルが起きやすくなります。
・肛門嚢炎:肛門嚢が炎症を起こし、腫れや痛みが出る状態
・肛門嚢破裂:肛門周辺の皮膚に穴があき、膿や血が出ることもある重度の状態
・肛門嚢肥大(とくに猫に多い):肛門嚢が硬く腫れ、触ると嫌がる
・肛門嚢の腫瘍:まれに悪性腫瘍が見つかることもあり、早期発見が重要
<こんなサインは要注意>
次のような様子がみられるときは、肛門嚢の中で炎症や肥大、破裂の前兆などが起きているおそれがあります。
・強いニオイがする
・お尻を触ると怒る/嫌がる
・お尻をしきりに舐める
・床にお尻をこすりつける
・絞ってもすぐに再発する
これらが続く場合、一度受診を検討していただくのが安心です。
保存療法で改善するケース・改善しないケース
肛門腺のトラブルは、初期であれば負担の少ない保存療法で改善が期待できます。たとえば、次のような治療が一般的です。
・肛門腺の圧迫排出(肛門腺絞り):たまった分泌物を外に出して炎症を落ち着かせます
・抗生剤・消炎剤の投与:細菌感染や炎症が強い場合に使用します
・洗浄:肛門嚢内に汚れや膿が溜まっている際に行います
ただし、保存療法だけでは改善が難しいケースもあります。次のような場合は、炎症が深く進んでいたり、別の病気が隠れているおそれがあります。
・何度も再発を繰り返す
・肛門嚢が破裂している(出血・膿・穴あき)
・肛門の周りがしこりのように固い
・絞ると強い痛みを示す
・肛門腺を絞ってもニオイが取れない
この段階まで進むと、炎症を消してもまたすぐ同じトラブルが起こりやすく、生活の質が大きく低下してしまいます。お尻を気にして眠れなかったり、触れられるだけで痛がったりと、飼い主様にとっても心配が尽きません。
慢性的な肛門腺トラブルが続く場合、肛門嚢摘出術が根本的な解決策になることがあります。手術によってその後の再発リスクを抑えることができ、長い目で見てその子の負担を減らすことにつながります。
肛門嚢摘出術とは?メリット・リスクについて
慢性的に肛門腺のトラブルを繰り返す場合、肛門嚢そのものが再発の原因になっていることがあります。肛門嚢摘出術は、その肛門嚢を丸ごと取り除くことで、根本からトラブルを解消するための手術です。
<手術の流れ>
流れのイメージは次のとおりです。
①…

猫の腎臓結石と尿管閉塞|見逃しやすい症状と最新の治療アプローチ
「なんとなく元気がない」「最近、いつもより食欲が落ちている気がする」
愛猫のそんな小さな変化の裏に「腎臓結石」や「尿管閉塞」といった深刻な泌尿器疾患が隠れていることがあります。
猫の上部尿路(腎臓〜尿管)に起こるトラブルは、尿の出口で起きる膀胱炎や尿道閉塞と違い、症状が非常にわかりにくいことが特徴です。気づかないうちに進行し、腎臓が急激にダメージを受けてしまうと、命に関わるケースもあります。
今回は、腎臓結石と尿管閉塞の特徴、注意すべき症状、診断・治療、再発予防について詳しく解説します。
■目次
1.腎臓結石・尿管閉塞とは?膀胱結石との違い
2.見逃せない症状|猫が見せる“危険のサイン”
3.診断と治療の考え方|早期判断で腎臓を守る
4.ご家庭でできる再発予防|“今日から始められる”ケア
5.まとめ
腎臓結石・尿管閉塞とは?膀胱結石との違い
尿路のトラブルと聞くと、膀胱炎や膀胱結石を思い浮かべる方が多いかと思います。しかし腎臓結石・尿管閉塞は、それより上流で起こる病気です。
・腎臓結石
腎臓の中に石(結石)ができる病気です。
水分摂取量の不足やミネラルバランスの乱れ、体質などが複雑に関わると考えられています。
・尿管閉塞
腎臓から膀胱へ尿を運ぶ細い管(尿管)に結石が詰まり、尿が流れなくなる状態です。
猫は尿管が特に細いため、ごく小さな結石でも閉塞を起こしやすいことが知られています。
<気づきにくい理由>
膀胱炎や尿道閉塞では「トイレに頻繁に行く」「尿が出ない」など分かりやすい変化が出ますが、腎臓結石・尿管閉塞では尿意の変化が少なく、初期はほとんど症状が見られません。
そのため、進行してから気付くケースが非常に多いのが問題点です。
また、腎臓は左右で2つあるため、片側の尿管が詰まっても表面上は普通に過ごしてしまうことがあります。しかし、残っている腎臓に負担がかかり続けると、将来的に慢性腎臓病を悪化させるリスクがあります。腎臓を守るうえでは、早期に正確な診断を受けることがとても大切です。
猫の慢性腎臓病について詳しく知りたい方はこちら
見逃せない症状|猫が見せる“危険のサイン”
腎臓結石・尿管閉塞でみられる症状には、次のようなものがあります。
・血尿(薄いピンク色程度でも注意が必要)
・嘔吐
・食欲が落ちる
・元気がない
・背中やお腹を触られるのを嫌がる
・排尿量が減っている
これらは比較的わかりやすいサインですが、実際にはもっと曖昧な変化しか出ないことの方が多い病気です。症状が軽そうに見える場合でも、内部では進行していることがあります。「いつもと違うかも…」という小さな変化は、受診の大切なサインになります。気になる点があれば早めにご相談ください。
また、腎臓や尿路のトラブルは症状が表れにくいこともあるため、定期的な健康診断(血液検査・エコー検査)で状態を確認しておくことが、予防や早期発見に役立ちます。
健康診断について詳しく知りたい方はこちら
<こんな症状が出ていたら緊急サイン>
以下に当てはまる場合は、体の内部で深刻なトラブルが起きているおそれがあります。
一刻を争う場合もあるため、少しでも当てはまる点があれば、すぐに動物病院にご相談ください。
・嘔吐を何度も繰り返す
・ぐったりして動かない
・尿がほとんど出ていない
気づいたときの早期受診と、症状が出る前からの定期的な健康チェックが、愛猫を守るいちばんの近道です。
診断と治療の考え方|早期判断で腎臓を守る
腎臓結石や尿管閉塞は、進行すると短時間で腎臓に大きな負担をかけてしまう病気です。そのため「どこで」「どの程度」問題が起きているかを正確に見きわめることが、治療の第一歩になります。
ナガワ動物病院では、症状が軽く見える場合でも、腎臓にダメージを残さないために必要な検査を組み合わせて早期判断につなげています。
<当院で行う主な検査>
原因を立体的に把握するために、次のような検査を組み合わせて実施します。
・血液検査:腎臓の働き・電解質のバランスを確認
・エコー(超音波)検査:結石の位置や尿管の閉塞状況をリアルタイムで評価
・レントゲン検査:結石の大きさ・数・位置を確認
・尿検査:尿の状態や結晶(結石のもと)を調べる
なかでもエコー検査は最も重要といっても良い検査です。猫の尿管は非常に細いため、数ミリの変化を正確に読み取る高度な観察技術が必要になります。
当院では高性能エコー機器と経験豊富な獣医師による読影技術により、早期発見・早期判断につながる精度の高い診断を行っています。
エコー検査について詳しく知りたい方はこちら
<治療の基本方針>
腎臓結石・尿管閉塞は「時間との勝負」という点が最大の特徴です。状態に応じて、次のような治療法から最適なものを選択します。
▼内科治療
結石が小さい、尿の通り道がまだ残っている、といった場合に実施します。
・点滴によるサポート
・痛みを抑える処置
・利尿剤で尿の流れを助ける
内科治療で改善する子もいますが、結石の位置・大きさ・閉塞の強さによっては、改善が難しい場合もあります。
なお、当院では人間の尿管結石の治療に用いる薬を用いて、治療を行っています。
▼外科治療(SUBシステム)
完全閉塞や重度の閉塞では緊急性が高く、外科的な処置が必要になる場合があります。
当院では腎臓と膀胱を細いチューブでつなぎ、尿管を迂回させて尿を流す…

【犬・猫の異物誤飲】吐かない・症状が出ないときも危険?飼い主様に知ってほしい判断基準
「さっきまであったおもちゃの一部がない」「落ちていたものを口に入れたのを見た」
そんな瞬間は、焦りで頭が真っ白になってしまうかもしれません。
犬や猫の異物誤飲は時間との勝負です。どれだけ早く正しい対応をとれるかが、命を守る大きなポイントになります。
今回は「異物を飲み込んだかもしれない」と気づいたその瞬間から、受診までに飼い主様ができる初動対応を中心にご紹介します。
■目次
1.異物誤飲に気づいたら、まず確認すべき3つのこと
2.絶対にしてはいけない自己判断の対処法
3.特に注意が必要な3つのケース
4.動物病院に連絡するとき、伝えるべき情報
5.異物誤飲を繰り返さないために、今日からできる予防習慣
6.まとめ
異物誤飲に気づいたら、まず確認すべき3つのこと
まずは深呼吸をして落ち着き、次の3点を確認しましょう。
①…

目の病気で“見えづらい・痛い”サインが出たら|ナガワ動物病院の眼科手術・検査体制
「最近、愛犬や愛猫の目の様子がおかしい」「目を気にしている仕草が増えた」──そのような変化を感じたことはありませんか?
目の病気は決して珍しいものではありません�…

犬が首を痛がる原因のひとつ|頸部椎間板ヘルニアの症状と治療選択肢
「椎間板ヘルニア」と聞くと「腰が痛くなる病気」というイメージを持つ方が多いかもしれません。ですが実は首にも起こることがあり、これを「頸部椎間板ヘルニア」と呼びます。
首に強い痛みを伴う病気ですが、犬は本能的に痛みを隠そうとすることがあるため、ご家庭では気づきにくいのが特徴です。
今回は、犬の頸部椎間板ヘルニアについて基本的な知識と、当院でご提案できる治療法についてご紹介します。
■目次
1.犬の頸部椎間板ヘルニアとは?
2.見逃しやすい症状
3.診断と治療の選択肢
4.ナガワ動物病院でできること
5.まとめ
犬の頸部椎間板ヘルニアとは?
背骨は小さな骨(椎骨)が連なってできています。その間にある椎間板はクッションのような役割を持ち、体を動かすときの衝撃を吸収して、背骨の中を通る大切な神経(脊髄)を守っています。
椎間板ヘルニアとは、この椎間板の一部が変性して外に飛び出し、脊髄を圧迫してしまう病気です。これが首で起こった場合を「頸部椎間板ヘルニア」と呼び、強い首の痛みや神経のトラブル(足のふらつきや麻痺など)につながることがあります。
「椎間板ヘルニア=腰の病気」と思われがちですが、首でも起こりうることは意外と知られていません。そのため発見が遅れてしまうケースもあります。早期に気づくためには「首にも起こりうる」ということを知っておくことがとても大切です。
また、この病気はミニチュア・ダックスフンドやフレンチ・ブルドッグなどの犬種で遺伝的に発症しやすいことが知られています。比較的若いうちに出ることもあり、一方で大型犬でも加齢によって発症するケースもあります。犬種や年齢にかかわらず注意が必要な病気といえるでしょう。
犬の胸腰部椎間板ヘルニアについて詳しく知りたい方はこちら
見逃しやすい症状
頸部椎間板ヘルニアは、初期の症状が小さく見えるため見過ごされてしまうことがあります。ご家庭で気づける代表的なサインには次のようなものがあります。
・頭を下げたまま上目遣いで見てくる
・小刻みに震える
・首を触ろうとすると嫌がって「ウー」とうなる
・首を動かしにくい様子で、食事や水を飲みにくそうにする
こうした行動は首の痛みによるものですが、腰や肩の不調と勘違いされたり、環軸亜脱臼など首の骨の異常や外傷と紛らわしいこともあります。
初めは首の痛みだけでも、病気が進むと足の麻痺や歩行のしづらさにつながることがあります。早い段階で気づいていただくことが、愛犬のつらさを減らし、重症化を防ぐ大切なポイントです。
診断と治療の選択肢
頸部椎間板ヘルニアは、症状の現れ方が犬によって異なるため、正確に診断するには動物病院での詳しい検査が欠かせません。
<診断の流れ>
診察は次のような流れで行われます。
・問診:普段の生活の様子や症状の出方をうかがいます
・身体検査:体を触って、痛みや違和感の有無を確認します
・神経学的検査:どの部位に異常があるか、進行度合いを判断します
・画像検査:レントゲン検査を行い、必要に応じてCT・MRIなどでさらに詳しく調べます
これらの検査結果を組み合わせて、発症部位や重症度を総合的に見極めます。
<治療について>
頸部椎間板ヘルニアは、症状の重さに応じて「ステージ」という段階に分けて考えることがあります。これは専門的な評価方法ですが、簡単にいうと「どのくらい症状が進んでいるか」を判断する目安です。
▼ステージ1〜2(軽度)
首の痛みはあるものの歩行は可能な状態です。この段階では、安静に過ごすことと痛みを和らげる投薬が基本になります。少なくとも4週間以上の安静が必要です。
▼ステージ3(重度)
麻痺や歩行困難が見られる段階です。この場合は外科手術を検討します。手術では飛び出した椎間板を取り除き、必要に応じて背骨に小さな穴を開けて脊髄への圧迫を和らげます。
このように、軽度であれば内科的な治療(安静+投薬)が中心、重度や再発例では外科的治療を考えるのが一般的な流れです。
ナガワ動物病院でできること
当院では、愛犬の状態に合わせて最適な治療法をご提案することを大切にしています。病気の進行度や生活の様子をふまえ、飼い主様と一緒に治療の方向性を考えていきます。
<内科治療>
ステージ2以下の比較的軽度な段階では、安静とお薬による治療を優先します。実際に、近年の研究ではこの段階では外科手術と内科治療の治療成績に大きな差がないと報告されています。まずは体への負担が少ない方法から取り組みます。
<外科手術>
内科治療で十分な改善が得られない場合や、強い痛み・麻痺がある場合には、提携病院と連携して外科手術をご紹介します。安全性に配慮しながら、適切なタイミングでご案内します。
<再生医療(幹細胞治療)>
炎症を抑えたり傷ついた組織の修復を助けたりする効果が期待される新しい治療法です。当院では幹細胞療法に対応できる環境を整えており、必要に応じてご提案できるのも強みのひとつです。
このように、当院では内科から外科、さらには再生医療まで幅広い選択肢をご用意しています。飼い主様とじっくり相談しながら、愛犬が少しでも快適に過ごせるように柔軟に治療方針を決めていきます。
まとめ
頸部椎間板ヘルニアは、腰のヘルニアと比べると認知度が低いため、気づかれにくく発見が遅れがちです。しかし進行すると強い痛みや麻痺を引き起こすこともあり、早期の発見と治療がとても大切です。
「最近首を気にしている」「動きがぎこちない」など気になる変化があれば、どうぞお気軽に当院へご相談ください。
<参考文献>
European…

繰り返す外耳炎に悩む愛犬・愛猫のために|全耳道切除術という治療選択肢について
「愛犬が耳をしきりにかいている」「愛猫の耳からにおいがする」といった耳のトラブルは珍しいことではなく、その多くは外耳炎によって起こります。実際に外耳炎は犬に非常に多い病気で、ペット保険の請求ランキングでも常に上位に入るほどです。
外耳炎は一度治っても再発を繰り返しやすく、放っておくと炎症が広がって治りにくくなることもあります。通常は点耳薬や内服薬で治療しますが、慢性化してしまった場合には「全耳道切除術」という手術が選択肢になることがあります。
今回は、外耳炎が繰り返される理由やその影響、そして全耳道切除術について詳しく解説します。
■目次
1.外耳炎とは?繰り返しやすい理由
2.繰り返す外耳炎がもたらす影響
3.どんな時に手術を検討するべき?
4.手術という選択肢|全耳道切除術(TECA)とは
5.ナガワ動物病院での手術以外のケア・選択肢について
6.まとめ
外耳炎とは?繰り返しやすい理由
犬や猫の耳は、私たち人間と同じようにいくつかの部位でできています。外から見える耳の部分を「耳介」、その奥に続く耳のトンネルを「外耳道」、さらに奥に鼓膜──という構造になっています。
外耳炎とは、この外耳道に炎症が起きてしまう病気のことです。原因はさまざまで、たとえば次のようなものが挙げられます。
・細菌やマラセチア(酵母菌)などの異常な増殖や感染
・耳ダニの寄生
・アレルギー体質(食物アレルギーや皮膚炎など)
・草の種や異物の侵入
といったものが知られています。犬でよくみられる印象がありますが、スコティッシュフォールドなど猫でも発症することがあるので注意が必要です。
さらに外耳炎には「繰り返しやすい」という特徴があります。
・耳が垂れていて蒸れやすい犬種や猫種では、耳の中が常に湿った状態になりやすい
・炎症が続くことで耳道の皮膚が厚くなり、通り道が狭くなってしまう
こうした要素が重なると「治ったと思ったのにまた再発する」という状況になりがちです。慢性化すると、耳のかゆみや痛みだけでなく、聞こえにくさや日常生活の質の低下にもつながるため、早めの対処が大切です。
犬の外耳炎について詳しく知りたい方はこちら
繰り返す外耳炎がもたらす影響
犬や猫にとっては、外耳炎が続くことで毎日の生活そのものが不快でつらいものになってしまいます。
・強いかゆみや痛みで耳をかいたり頭を振ったりする
・常に違和感があり、落ち着かなくなる
・耳が聞こえにくくなる
・重症化すると鼓膜が破れ、中耳炎に進行することもある
また、飼い主様にとっても負担は小さくありません。「治療を続けてもなかなか良くならない」という不安や、繰り返す通院による時間的な負担、長引く治療費による経済的な負担が積み重なっていきます。
このように、繰り返す外耳炎は犬や猫にも飼い主様にも影響を及ぼす大きな問題です。改善が難しい場合には、次の治療選択肢を検討することが大切になります。
どんな時に手術を検討するべき?
外耳炎の多くは点耳薬や内服薬といった内科的な治療で改善が見込めます。ですが、中には薬だけでは治らないケースもあります。そのようなときには、手術という選択肢を検討することがあります。
たとえば…
・炎症が中耳や内耳にまで広がり、ふらつきやめまいなどの神経症状が出ている場合
・繰り返す炎症で耳道が厚くなり、薬が届かなくなってしまった場合
・耳道内に炎症性ポリープや腫瘍ができて、耳の通り道がふさがってしまっている場合
このようなときに「全耳道切除術(TECA)」という外科的な方法が治療の選択肢のひとつになるのです。
手術という選択肢|全耳道切除術(TECA)とは
全耳道切除術(TECA)は、耳道全体を取り除き、炎症や感染の原因そのものをなくしてしまう手術です。
<全耳道切除術の流れ>
手術の流れを簡単にご紹介します。
1.…

犬と猫の認知症|よくある初期症状と進行をおだやかにするケアの選択肢
私たち人間と同じように、犬や猫も昔と比べて寿命が延びて長生きするようになりました。
その一方で、加齢に伴う病気も増えており、特に飼い主様を悩ませるもののひとつが「認知症」です。発症してしまうと完治は難しいものの、早い段階で気づき、適切なケアを取り入れることで進行をゆるやかにできる可能性があります。
今回は犬と猫の認知症について、見逃しやすい初期症状やケアの選択肢を詳しく解説します。
■目次
1.犬と猫にも認知症はある?
2.見逃しやすい初期症状とよくある行動
3.治療・ケアの選択肢
4.進行をゆるやかにするために
5.まとめ
犬と猫にも認知症はある?
認知症とは、加齢によって脳の機能が低下し、記憶や行動に異常が出る状態を指します。
犬の場合は「認知機能不全症候群(CDS)」とも呼ばれ、特に10歳を超えるシニア犬に多くみられます。また猫も15歳前後から同様の症状が出やすいといわれていますが、発症年齢には個体差があるため、若い年齢でも注意が必要です。
見逃しやすい初期症状とよくある行動
認知症になると、次のような行動や変化がみられることがあります。
・昼夜逆転(昼間に眠り、夜に活動的になる)
・夜鳴きや無駄吠えが増える
・同じ場所をぐるぐると徘徊する
・トイレの失敗が増える
・飼い主様を認識できなくなる
・隅に頭を突っ込んだまま動かない
こうした変化は、飼い主様が「年のせいかな」と見過ごしてしまうことも少なくありません。気になるサインがあれば、セルフチェックで確認するのもひとつの方法です。
▼参考(外部サイト)
DISHAAチェック(犬の認知症セルフチェック)
このチェック方法では、犬や猫の行動をいくつかの項目に分けて点数化します。
たとえば、
☑…

犬の鼠経ヘルニア・臍ヘルニアとは?放置のリスクと治療法を獣医師が解説
愛犬のお腹や後ろ足の付け根に膨らみを見つけると「太ったのかな?」「腫瘍だったらどうしよう…」と不安になる飼い主様も多いのではないでしょうか。
実はその膨らみは「�…

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは|犬・猫にも感染するマダニ感染症の症状と予防策
当院からの大切なお知らせ
SFTSが疑われる犬猫は、直接ご来院いただくことができません。
まずは必ずお電話にて当院へご相談ください。
外に出ている猫ちゃんはしばらく外出を控えていただき、症状がある場合も院内には連れて来ず、事前にご連絡をお願いいたします。 近年、ニュースなどでも耳にすることが増えてきた「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」。マダニが媒介するこの感染症は、人だけでなく犬や猫などの動物にも感染・発症することが知られており、注意が必要です。
今回は、SFTSの基礎知識や犬・猫で見られる症状、ご家庭でできる予防対策について、獣医師の視点から詳しく解説します。
■目次
1.SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは?
2.マダニはどこにいる?身近に潜むリスク
3.マダニ感染を防ぐには?ご家庭でできる予防対策
4.ご来院について
5.まとめ
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは?
SFTS(Severe…

暑い時期の皮膚トラブルにご注意を|犬や猫のかゆみ・皮膚炎の原因と治療・薬浴ガイド
いよいよ暑い夏がやってきました。湿気や気温の上昇によって皮膚の環境が悪化しやすくなるこの季節、犬や猫にとって皮膚病は特に注意が必要です。脱毛やかゆみなどのトラブルは、生活の質を下げるだけでなく、強いストレスの原因にもなります。
今回は、夏に増える皮膚病の原因や症状、ご家庭でできるケア方法に加え、ナガワ動物病院での対応について詳しくご紹介します。
■目次
1.暑い時期に多い犬と猫の皮膚トラブル|主な原因とは?
2.こんなときは受診を|ご家庭でのケアと病院受診の境界線
3.病院での治療とトリミングの役割|ナガワ動物病院の対応
4.まとめ
暑い時期に多い犬と猫の皮膚トラブル|主な原因とは?
夏は気温と湿度の上昇により、犬や猫の皮膚トラブルが起きやすい季節です。以下のような原因がよく見られます。
<ノミ・ダニによる皮膚炎>
ノミやダニなどの外部寄生虫は、夏の高温多湿な環境で繁殖しやすくなります。寄生されることで強いかゆみや皮膚炎を引き起こし、なかにはアレルギー反応を起こすケースも。
外出する犬だけでなく、室内で過ごす猫でも感染することがあるため、年間を通じた予防が大切です。
<皮膚バリア機能の低下>
健康な皮膚はバリア機能によって外部の刺激から体を守っています。しかし、夏の蒸し暑さによってその機能が弱まり、通常なら発症しないような皮膚病にかかりやすくなります。
また、近年の研究では、腸内環境とアレルギー性皮膚炎の関係性も注目されています。当院では、乳酸菌製剤を含むサプリメントによる「腸活」もご提案しています。
<雑菌の繁殖や皮脂の分泌異常>
暑さや湿気によって皮脂の分泌が増えると、皮膚に常在する菌(マラセチアやブドウ球菌など)が過剰に増殖し、皮膚炎を引き起こすことがあります。
蒸れやすい部分(脇の下、足の付け根、耳の中など)は特に注意が必要です。
<紫外線による皮膚へのダメージ>
白毛や短毛の犬種(ブルテリアなど)では、紫外線の影響を受けやすい傾向があります。長時間日光を浴びることで、皮膚が赤くなるだけでなく、まれに扁平上皮癌などの重大な疾患につながることもあります。
夏に見られる皮膚の不調の裏にはこうした背景があることを知っておくと、早めの対応にもつながります。
<皮膚糸状菌症(真菌感染症)の多発>
近年、夏の高温多湿な環境で真菌による皮膚病(皮膚糸状菌症)が多発しています。
この病気はかゆみや脱毛、赤みを引き起こすだけでなく、ステロイド薬を使用すると症状が悪化するため、一般的な皮膚炎とは異なる注意が必要です。
特に2025年夏は例年に比べて発生が目立っており、早期の診断と適切な治療が重要です。
また、当院では皮膚糸状菌症のような真菌感染症が疑われる場合、診察時から待合室・診察室でのカビ拡散防止を徹底しています。
また、毎日院内の清掃・消毒を行い、安心して通院いただける環境を整えていますので、お気軽にご相談ください。
こんなときは受診を|ご家庭でのケアと病院受診の境界線
皮膚病の予防には、日々のちょっとしたケアの積み重ねがとても大切です。特に夏場は、以下のようなポイントを意識することで、皮膚トラブルのリスクを減らすことができます。
・適切な頻度でのシャンプー
皮膚の汚れや余分な皮脂を落とすことで、雑菌の繁殖を防ぎます。ただし、洗いすぎは逆効果になることもあるため、シャンプーの頻度や使用する製品は、愛犬・愛猫の皮膚の状態に合わせて選びましょう。
・室内の温度・湿度の管理
高温多湿の環境は、皮膚病を引き起こす大きな要因です。室温は25℃前後、湿度は50〜60%を目安に、エアコンや除湿器を活用しながら快適な環境を整えてあげましょう。風通しを良くする工夫や、クールマットの設置もおすすめです。
・ノミ・ダニの予防
ノミやマダニは、かゆみや皮膚炎の原因になるだけでなく、重篤な感染症を媒介することもあります。草むらに入らなくても寄生することがあるため、室内飼育の犬や猫でも油断はできません。予防薬を定期的に使って、しっかり対策してあげましょう。
ノミ・マダニ予防について詳しく知りたい方はこちら
・毎日のブラッシング
被毛を整えることに加えて、皮膚の異変に早く気づくきっかけにもなります。抜け毛やフケ、赤み、湿った部分などを日々の中でチェックすることで、トラブルを未然に防げることもあります。特に脇の下や足の付け根、首まわりなどは蒸れやすいため、意識的にケアしてあげましょう。
<こんな症状が見られたら早めのご相談を>
どれだけ丁寧にケアをしていても、皮膚病が進行してしまうことはあります。以下のような症状が見られる場合は、悪化を防ぐためにも早めの受診をおすすめします。
・食事中や散歩中、睡眠中にかゆがる様子がある
・脱毛やフケ、皮膚の赤みや黒ずみといった変化が見られる
・においが強くなる(皮膚が蒸れたような不快なにおいなど)
・皮膚にかさぶたや出血がある
・元気や食欲がなくなる、体重が落ちるなどの全身症状を伴う
こうした変化は、皮膚の炎症や感染が進んでいるサインかもしれません。初めは軽く見えても、放っておくことで炎症が広がり、かゆみが強くなったり、治療に時間がかかってしまうこともあります。
また、皮膚病の中には「イッチ・スクラッチ・サイクル」と呼ばれる悪循環が知られています。これは「かゆみ…