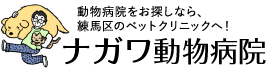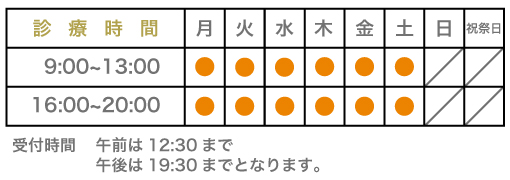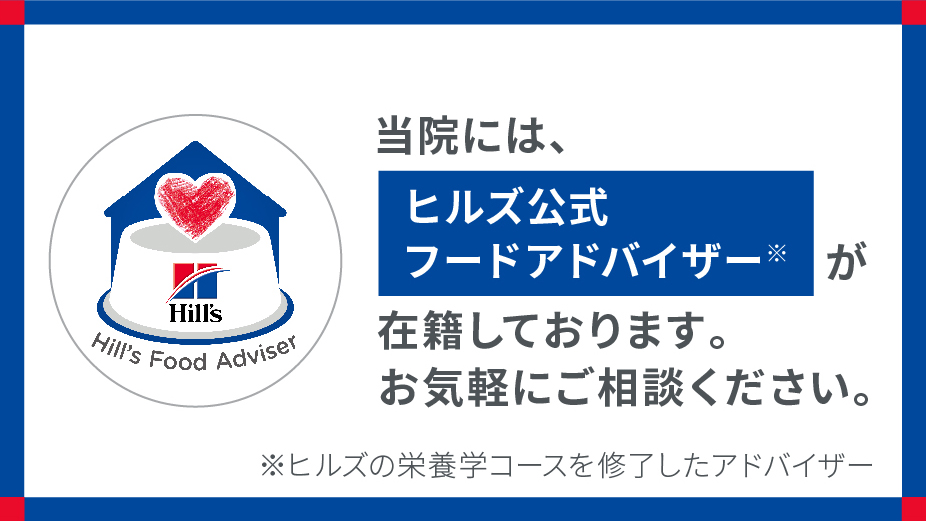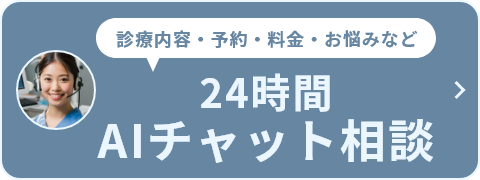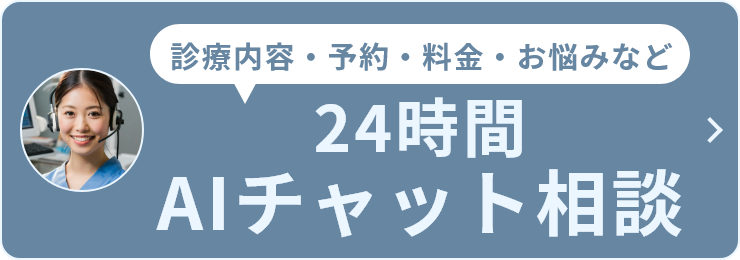犬の鼠経ヘルニア・臍ヘルニアとは?放置のリスクと治療法を獣医師が解説
愛犬のお腹や後ろ足の付け根に膨らみを見つけると「太ったのかな?」「腫瘍だったらどうしよう…」と不安になる飼い主様も多いのではないでしょうか。
実はその膨らみは「鼠経(そけい)ヘルニア」や「臍(さい)ヘルニア」かもしれません。どちらも先天的に起こることが多い病気で、腸が挟まって炎症を引き起こし、命に関わる状態に至ることもあります。
今回は、犬の鼠経ヘルニアと臍ヘルニアの違いや共通点、放置してはいけない理由、そしてナガワ動物病院で行っている治療方法について詳しく解説します。
鼠経ヘルニア・臍ヘルニアとは?
まず「ヘルニア」とは、本来であれば臓器を支えている壁に小さな穴(ヘルニア門)ができ、腸や脂肪などの組織が皮膚の下に飛び出してしまう状態をいいます。犬に見られるヘルニアにはいくつか種類がありますが、その中でも代表的なのが「鼠経ヘルニア」と「臍ヘルニア」です。
◆鼠経ヘルニア
後ろ足の付け根(鼠径部)にできるヘルニアです。
生まれつき(先天性)のものは若いオス犬で見られることが多く、加齢や出産などに伴って起こる(後天性)のものはメス犬に多いとされています。
◆臍ヘルニア
おへその部分(臍部)に発生するヘルニアで、いわゆる「でべそ」もその一つです。
先天的にお腹の壁がしっかり閉じきらなかったことが原因で起こるケースが多く、子犬でよく見られます。
<鼠経ヘルニアと臍ヘルニアの違い>
両者は一見似ているように思えますが、触ったときの感触やリスクに違いがあります。
・触ったときの感触や形状
どちらも柔らかいしこりのように感じられますが、鼠経ヘルニアは臍ヘルニアより深部にあり、膨らみが大きく感じられることがあります。
・リスクの違い
鼠経ヘルニアは、腸閉塞や臓器の壊死など深刻な合併症に発展しやすいといわれています。臍ヘルニアでも腸が入り込むと危険ですが、相対的にはリスクが低めです。
<共通する特徴>
鼠経ヘルニアと臍ヘルニアには、いくつかの共通点があります。
まず、どちらも皮膚のふくらみや柔らかいしこりとして飼い主様が気づくことが多い病気です。膨らみの大きさはケースによって異なり、小さな粒のように感じられることもあれば、指で押すと戻るような柔らかさを伴う場合もあります。
また、犬では先天的に生まれつき持っているケースが少なくありません。見た目には軽く見えることもありますが、自然に治ることはほとんどなく、専門的な診断が欠かせない点も両者に共通しています。
放置してはいけない理由
鼠経ヘルニアや臍ヘルニアは、見た目が小さな膨らみであっても油断はできません。そのままにしておくと、思わぬトラブルにつながることがあるため注意が必要です。
<鼠経ヘルニアで起こり得ること>
鼠経部に発生するヘルニアでは、飛び出した腸や脂肪が締めつけられることで血流が悪くなり、腸閉塞や壊死を引き起こす危険があります。特にメス犬では、まれに子宮が飛び出してしまうケースもあり、緊急性が高まることがあります。
<臍ヘルニアで起こり得ること>
おへその部分にできる臍ヘルニアでも、腸が巻き込まれたり感染を起こしたりするリスクがあります。膨らみが小さい場合でも、経過を見守りながら獣医師に相談しておくことが安心につながります。
膨らみが小さいうちは症状が目立たなくても、突然悪化することがあります。様子を見るのではなく、早めに獣医師へ相談することが大切です。
治療方法とナガワ動物病院の対応
鼠経ヘルニアや臍ヘルニアは、自然に治ることはほとんどありません。根本的な治療には外科手術でヘルニア門を閉鎖することが必要です。手術は全身麻酔のもとで行い、飛び出した組織をお腹に戻し、穴をふさぐことで再発を防ぎます。
・鼠経ヘルニア:オス犬に併発しやすい停留精巣の摘出と合わせて行うこともあります。
・臍ヘルニア:進行によるトラブルを避けるため、避妊手術と同時に整復するケースが多くあります。
<手術のタイミング>
「いつ手術をすべきか」は、犬の年齢や体調、ヘルニアの大きさ・状態によって異なります。成長段階にある若い犬では、早めの対応が望ましい場合もあれば、小さい臍ヘルニアや、手術リスクが高い高齢犬では、あえて経過観察を選ぶこともあります。
こうした判断には専門的な視点が欠かせないため、定期的なチェックを続けながら最適なタイミングを見極めていきます。
<ナガワ動物病院での取り組み>
当院では、外科手術の際に犬への負担をできるだけ減らすことを大切にしています。
・術前検査でリスクをしっかり把握し、安全性に配慮した麻酔管理を実施
・術後の回復を支えるため、痛み止めを含めた徹底した鎮痛ケア
・避妊手術や停留精巣の摘出と同時に行い、麻酔の回数を減らす工夫
手術そのものだけでなく、前後のケアやライフステージに合わせた判断を含めて、安心していただける治療を心がけています。
まとめ
鼠経ヘルニアや臍ヘルニアは、一見すると小さな膨らみに見えることが多い病気です。しかし、放置すると腸閉塞や感染など思わぬトラブルにつながるおそれがあり、自然に治ることはほとんどありません。
根本的な治療には外科手術が必要ですが、そのタイミングや方法は犬の年齢・体調・ヘルニアの状態によって異なります。経過観察を選ぶケースも含めて、一頭ごとに最適な方針を決めていくことが大切です。
「うちの子の膨らみは大丈夫かな?」と少しでも不安に思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。
⏬よろしければ、星のボタンでこの記事の感想を教えてください⏬
🔳以下の関連記事もご覧ください
犬や猫の会陰ヘルニアについて│未去勢の高齢犬によくみられる疾患、予防には早期の去勢手術が重要!
ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院
03-3926-9911