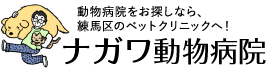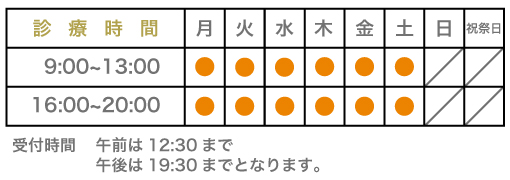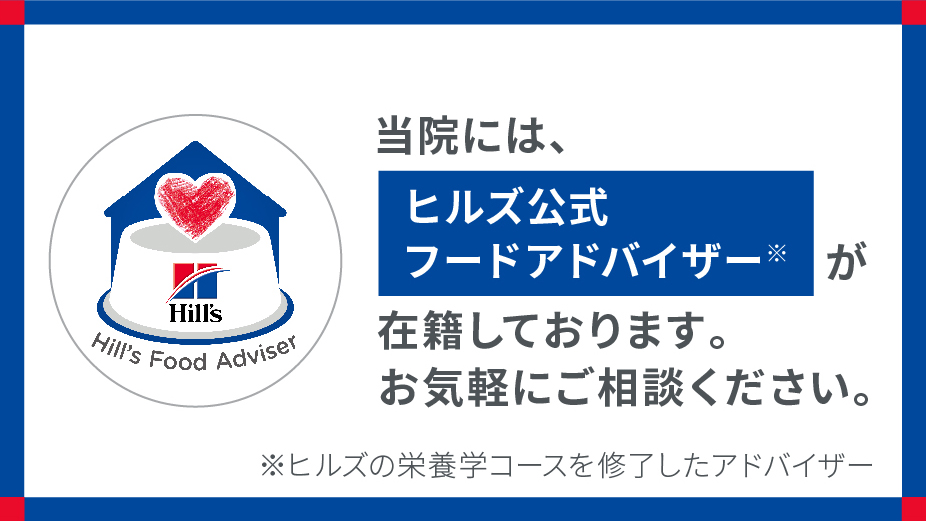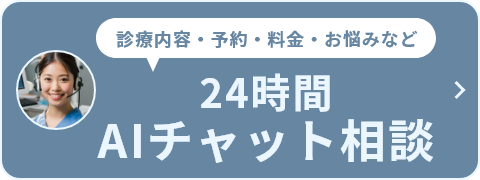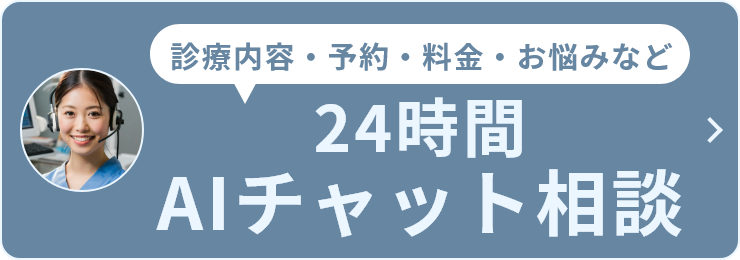【獣医師監修】猫の慢性腎臓病 – ステージ別食事管理と自宅でできるケア方法
慢性腎臓病は特にシニア猫に多く見られる病気で、腎臓の機能が徐々に低下していく進行性の疾患です。早期発見が難しく、症状が現れたときには病気がかなり進行していることが多いという特徴があります。しかし、適切な食事管理や在宅ケアを早くから始めることで、病気の進行を遅らせ、愛猫の生活の質(QOL)を維持することができます。
慢性腎臓病は根治が難しいため、診断を受けた飼い主様はショックを感じるかもしれません。しかし、まずはできることから始め、愛猫との生活を少しでも長く楽しむために、一緒に向き合っていきましょう。
今回は、猫の慢性腎臓病について、病気の基礎知識や症状、診断方法、在宅ケアのポイントなどを詳しく解説します。
猫の慢性腎臓病とは?基本的な理解
腎臓は、体内の老廃物を排出し、水分やミネラルのバランスを調整する重要な臓器です。慢性腎臓病ではこれらの機能が徐々に低下し、以下のような問題が発生します。
・老廃物排出が困難になる
・脱水やミネラル異常、血圧の上昇が起こる
・心臓に負担がかかり、肥大型心筋症を併発することがある
慢性腎臓病は中高齢の猫で特に多く、5~6歳以降に発症リスクが高まります。多くの場合は加齢による腎機能の低下が原因ですが、尿石症などの泌尿器の病気が原因となることもあります。また、まれに先天的な腎臓の奇形によって発症するケースがあります。
愛猫の慢性腎臓病に早く気づくためのサイン
慢性腎臓病の初期には目立った症状がほとんどありませんが、腎臓の機能が低下すると次のようなサインが現れ始めます。
・多飲多尿:水をたくさん飲み、おしっこの量が増える
・食欲低下:食事を残す、興味を示さなくなる
・体重減少:体格がほっそりし、あばらが浮き出る
・被毛の艶の低下:毛並みがぼさぼさになり、艶が失われる
慢性腎臓病が進行すると、さらに重篤な症状が現れることがあります。
・口臭:アンモニア臭がする
・高血圧:目が赤くなる、心臓のリズムに異常が出る
・神経症状:けいれんや神経過敏
これらの症状は他の病気でも見られることがあるため、自己判断は危険です。確実な診断のもとで治療を進めていくためにも、異変を感じたら、まずは動物病院で適切な検査を受けましょう。
慢性腎臓病の診断とステージ分類
慢性腎臓病を正確に診断するためには、以下の検査が必要です。
・血液検査:BUN、クレアチニン、SDMAなど腎機能を示す数値を確認
・尿検査:尿比重や尿たんぱくなどを測定
・血圧測定:腎臓への負担を評価
・エコー検査:腎臓の状態を画像で確認
これらの検査結果を総合的に判断し、慢性腎臓病の進行度を評価します。
進行度は「国際腎臓病学会(IRIS)」によってステージ1〜4に分類されており、ステージごとに治療方針が異なります。そのため、定期的に検査を実施し、愛猫がどのステージにあるのかを把握することが大切です。
<慢性腎臓病のステージ分類>
ステージ1:腎障害はあるものの、一般的に無症状。腎機能は33%以上。
ステージ2:無症状もしくは軽い症状が現れる。腎機能は25~33%。
ステージ3:さまざまな症状が出現。腎機能は10~25%。
ステージ4:重度の症状が現れる。腎機能は5~10%。
<治療方針と定期検査の重要性>
慢性腎臓病の治療では、病気の進行をできるだけ遅らせ、愛猫が快適に過ごせるようにサポートすることが目標です。特に重要なのが、ステージ2以下の状態をいかにキープするかという点です。
飼い主様の中には、「ステージ2だからまだ大丈夫」と安心される方もいらっしゃいますが、実際にはステージ2の時点で腎機能の7割が失われているため、決して油断できない状況です。腎臓の機能は一度低下すると回復が難しく、放置すると急速に悪化するリスクがあるため、ステージの初期段階で治療を始めることが非常に重要です。
当院では、慢性腎臓病が発症した際には、できる限りステージ2以下の状態を維持できるように治療プランを策定しています。定期検査を通じて進行具合を把握し、状況に応じた対策を講じることで、愛猫の健康をサポートいたします。
ステージ別の在宅ケアや食事管理の重要性
慢性腎臓病は進行性の病気であるため、ステージに応じた適切なケアが欠かせません。
特に食事療法は、慢性腎臓病の管理において最も重要な要素の一つです。腎臓への負担を減らすためには、たんぱく質、リン、ナトリウムの量を調整することが求められますが、筋肉量が減少するとかえって病状が悪化するリスクもあるため、バランスの取れた管理が必要です。当院では、腎臓の数値を上げないように工夫しながら、適度なたんぱく質も補えるような食事指導を行っています。
さらに、近年注目されているAIMたんぱく質の摂取が腎臓病の進行抑制につながる可能性が指摘されており、今後の治療選択肢として期待されています。
<ステージ別ケアのポイント>
慢性腎臓病の管理では、病気の進行を遅らせるための予防的ケアから、症状を和らげるためのサポート、終末期のQOL維持まで、各ステージに応じたアプローチが求められます。
▼初期(ステージ1~2):予防的ケアと食事管理
この段階では予防的ケアを中心に考えます。たんぱく質やリン、ナトリウムの含有量を抑えた腎臓病用療法食を取り入れることで、腎臓への負担を減らす効果が期待できます。
また、食事だけでなく水分補給を意識することが重要です。特に猫はもともと水をあまり飲まないため、ウエットフードやふやかしたドライフードを与えるなどして、水分摂取量を増やす工夫をしましょう。
▼中期(ステージ3):症状緩和を目的としたケア
ステージ3になると、症状が顕著になりやすいため、症状緩和を重視したケアが求められます。特に貧血や消化器症状が現れることがあり、食欲が低下しやすいため、嗜好性の高い療法食や、フードを温めて香りを引き立たせる工夫が効果的です。
また、水分摂取をより意識し、スープタイプのフードや水分を多く含むウエットフードを活用することで、脱水を防ぎ腎機能をサポートします。栄養が偏らないように、獣医師の指導のもとでサプリメントを適切に使いながらケアを進めましょう。
▼末期(ステージ4):QOL維持を目指すケア
末期段階では、愛猫ができるだけ快適に過ごせる環境を整えることが最優先です。
この時期には、食欲が極端に低下することが多く、必要に応じて栄養チューブの使用を検討します。無理に食べさせるのではなく、少量でも摂取できる工夫が重要です。
また、体調の変化が激しい時期ですので、こまめな体調チェックと痛みや不快感の管理を徹底しましょう。獣医師と連携しながら、適切な治療プランを調整していくことが大切です。
まとめ
慢性腎臓病は進行性の病気ですが、早期発見と適切な管理を行うことで、病気の進行を遅らせ、愛猫が穏やかに過ごせる時間を延ばすことが期待できます。
特に食事管理や在宅ケアは、慢性腎臓病の管理において最も重要な要素です。ご家庭でのケアを怠ってしまうと、病気が進行してしまい、愛猫が非常に苦しい最期を迎えてしまうケースも少なくありません。当院でも、症状が進んでからご相談に来られ「もっと早くケアを始めていれば」と後悔される飼い主様を何度も見てきました。この記事をご覧の飼い主様には、同じ後悔をしてほしくないと心から願っています。
愛猫の健康を守るためには、少しでも気になる変化があれば早めに動物病院を受診し、一日でも早く適切なケアを始めることが大切です。気になる症状がある際には、ぜひ当院にもお気軽にご相談ください。丁寧な診断とサポートを通じて、愛猫と飼い主様が少しでも長く快適に過ごせるようお手伝いさせていただきます。
<参考文献>
原田佳代子. 6.慢性腎臓病. In: 犬と猫の腎臓病診療ハンドブック. 上地正実 監修. 2021 : pp.104-123. 緑書房.
🔳以下の関連記事もご覧ください
犬と猫の健康診断について┃1日でも長く愛犬愛猫と暮らすためにも…
ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院
03-3926-9911