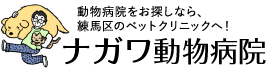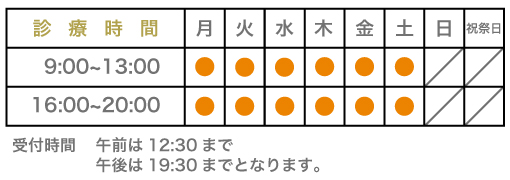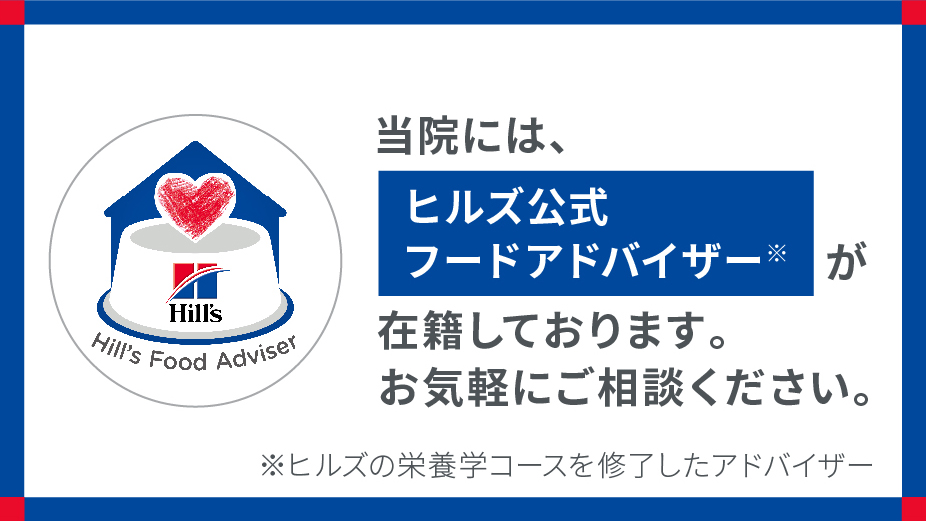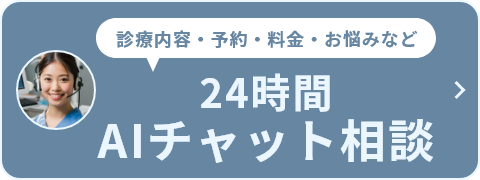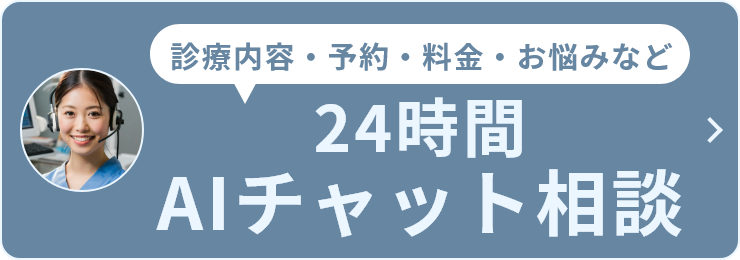暑い時期の皮膚トラブルにご注意を|犬や猫のかゆみ・皮膚炎の原因と治療・薬浴ガイド
いよいよ暑い夏がやってきました。湿気や気温の上昇によって皮膚の環境が悪化しやすくなるこの季節、犬や猫にとって皮膚病は特に注意が必要です。脱毛やかゆみなどのトラブルは、生活の質を下げるだけでなく、強いストレスの原因にもなります。
今回は、夏に増える皮膚病の原因や症状、ご家庭でできるケア方法に加え、ナガワ動物病院での対応について詳しくご紹介します。
暑い時期に多い犬と猫の皮膚トラブル|主な原因とは?
夏は気温と湿度の上昇により、犬や猫の皮膚トラブルが起きやすい季節です。以下のような原因がよく見られます。
<ノミ・ダニによる皮膚炎>
ノミやダニなどの外部寄生虫は、夏の高温多湿な環境で繁殖しやすくなります。寄生されることで強いかゆみや皮膚炎を引き起こし、なかにはアレルギー反応を起こすケースも。
外出する犬だけでなく、室内で過ごす猫でも感染することがあるため、年間を通じた予防が大切です。
<皮膚バリア機能の低下>
健康な皮膚はバリア機能によって外部の刺激から体を守っています。しかし、夏の蒸し暑さによってその機能が弱まり、通常なら発症しないような皮膚病にかかりやすくなります。
また、近年の研究では、腸内環境とアレルギー性皮膚炎の関係性も注目されています。当院では、乳酸菌製剤を含むサプリメントによる「腸活」もご提案しています。
<雑菌の繁殖や皮脂の分泌異常>
暑さや湿気によって皮脂の分泌が増えると、皮膚に常在する菌(マラセチアやブドウ球菌など)が過剰に増殖し、皮膚炎を引き起こすことがあります。
蒸れやすい部分(脇の下、足の付け根、耳の中など)は特に注意が必要です。
<紫外線による皮膚へのダメージ>
白毛や短毛の犬種(ブルテリアなど)では、紫外線の影響を受けやすい傾向があります。長時間日光を浴びることで、皮膚が赤くなるだけでなく、まれに扁平上皮癌などの重大な疾患につながることもあります。
夏に見られる皮膚の不調の裏にはこうした背景があることを知っておくと、早めの対応にもつながります。
<皮膚糸状菌症(真菌感染症)の多発>
近年、夏の高温多湿な環境で真菌による皮膚病(皮膚糸状菌症)が多発しています。
この病気はかゆみや脱毛、赤みを引き起こすだけでなく、ステロイド薬を使用すると症状が悪化するため、一般的な皮膚炎とは異なる注意が必要です。
特に2025年夏は例年に比べて発生が目立っており、早期の診断と適切な治療が重要です。
また、当院では皮膚糸状菌症のような真菌感染症が疑われる場合、診察時から待合室・診察室でのカビ拡散防止を徹底しています。
また、毎日院内の清掃・消毒を行い、安心して通院いただける環境を整えていますので、お気軽にご相談ください。
こんなときは受診を|ご家庭でのケアと病院受診の境界線
皮膚病の予防には、日々のちょっとしたケアの積み重ねがとても大切です。特に夏場は、以下のようなポイントを意識することで、皮膚トラブルのリスクを減らすことができます。
・適切な頻度でのシャンプー
皮膚の汚れや余分な皮脂を落とすことで、雑菌の繁殖を防ぎます。ただし、洗いすぎは逆効果になることもあるため、シャンプーの頻度や使用する製品は、愛犬・愛猫の皮膚の状態に合わせて選びましょう。
・室内の温度・湿度の管理
高温多湿の環境は、皮膚病を引き起こす大きな要因です。室温は25℃前後、湿度は50〜60%を目安に、エアコンや除湿器を活用しながら快適な環境を整えてあげましょう。風通しを良くする工夫や、クールマットの設置もおすすめです。
・ノミ・ダニの予防
ノミやマダニは、かゆみや皮膚炎の原因になるだけでなく、重篤な感染症を媒介することもあります。草むらに入らなくても寄生することがあるため、室内飼育の犬や猫でも油断はできません。予防薬を定期的に使って、しっかり対策してあげましょう。
・毎日のブラッシング
被毛を整えることに加えて、皮膚の異変に早く気づくきっかけにもなります。抜け毛やフケ、赤み、湿った部分などを日々の中でチェックすることで、トラブルを未然に防げることもあります。特に脇の下や足の付け根、首まわりなどは蒸れやすいため、意識的にケアしてあげましょう。
<こんな症状が見られたら早めのご相談を>
どれだけ丁寧にケアをしていても、皮膚病が進行してしまうことはあります。以下のような症状が見られる場合は、悪化を防ぐためにも早めの受診をおすすめします。
・食事中や散歩中、睡眠中にかゆがる様子がある
・脱毛やフケ、皮膚の赤みや黒ずみといった変化が見られる
・においが強くなる(皮膚が蒸れたような不快なにおいなど)
・皮膚にかさぶたや出血がある
・元気や食欲がなくなる、体重が落ちるなどの全身症状を伴う
こうした変化は、皮膚の炎症や感染が進んでいるサインかもしれません。初めは軽く見えても、放っておくことで炎症が広がり、かゆみが強くなったり、治療に時間がかかってしまうこともあります。
また、皮膚病の中には「イッチ・スクラッチ・サイクル」と呼ばれる悪循環が知られています。これは「かゆみ → 掻く → 炎症 → さらにかゆくなる」という連鎖のことで、愛犬・愛猫にとって大きなストレスになります。こうした状態を断ち切るために、アポキルやゼンレリアといったかゆみ止めのお薬を使うこともあります。
違和感に気づいた時点でご相談いただくことが、症状の進行を防ぎ、愛犬・愛猫の負担を最小限に抑えることにつながります。
病院での治療とトリミングの役割|ナガワ動物病院の対応
ナガワ動物病院では、皮膚病の診療において「原因の特定」と「状態に応じた適切な治療」を重視しています。診察ではまず飼い主様からご家庭での様子を詳しくうかがい、皮膚の状態を確認する検査(視診・皮膚検査・掻爬検査など)を行ったうえで、治療方針を決定します。
治療の選択肢は幅広く、以下のような方法を症状や体質に応じて組み合わせています。
・抗菌薬・抗真菌薬
・抗炎症薬・かゆみ止め
・保湿・抗炎症作用のある薬用シャンプー
・サプリメントや食事療法
また、皮膚病の治療では、トリミングも大きな役割を果たします。
当院では犬専用のトリミングサービスを併設しており、皮膚の状態を整えるためのスキンケアを獣医師と連携してご提案しています。
<医療と連携したトリミングケア>
皮膚の状態や体質に合わせ、以下のようなスキンケアをご提案しています。
・薬浴、ウルトラファインバブル、炭酸泉などの専門的な皮膚ケア
・セラミドやプロテオグリカンを含んだ保湿性の高いシャンプーを使用
・低刺激のオイルクレンジングで皮脂汚れやにおいのケアも可能
シャンプーには、肛門腺しぼり・爪切り・足裏バリカン・耳洗浄などの基本的な処置も含まれており、皮膚の健康をトータルにサポートします。
また、施術中もトリマーが皮膚の状態を細かく観察しており、異変に気づいた際はすぐに獣医師に相談できる体制を整えています。
<持病のある子やシニアの子にも安心の体制>
持病のある子やシニアの子も、トリミング前には必ず獣医師が健康状態を確認したうえで、できる限り対応しています。寝たきりの子でも施術できる専用の設備もあり、ご安心いただける環境です。
<暮らしに寄り添うカウンセリング>
施術前のカウンセリングでは、スタイルブックやタブレットを活用してカットの仕上がりをすり合わせています。「食事のときに顔まわりが汚れる」「足が拭きにくい」といった日常のお困りごともお気軽にご相談ください。愛犬にも飼い主様にもやさしいスタイルをご提案しています。
実際に、トリミングやシャンプーのみで皮膚の状態が改善するケースも多く、適切なスキンケアが治療の一環として効果を発揮することもあります。
当院のトリミング・シャンプーについて詳しく知りたい方はこちらから
まとめ
犬や猫にとって、日本の蒸し暑い夏は皮膚病が起こりやすい季節です。ノミ・ダニ、雑菌の繁殖、蒸れ、紫外線など、さまざまな要因が皮膚に負担をかけます。
特に真菌感染症は、見た目が一般的な皮膚炎と似ているため、自己判断での市販薬やステロイド使用は危険です。
当院でも今年は皮膚糸状菌症の症例が例年より多く、症状が気になる場合は早めの受診をおすすめします。
大切なのは、日常のスキンケアと環境管理、そして気になる症状があるときには早めに動物病院を受診することです。さらに、トリミングを上手に取り入れることで、皮膚の健康を保ちやすくなります。
皮膚の赤みやかゆみなど、気になる症状があれば、どうぞお気軽にナガワ動物病院までご相談ください。
⏬よろしければ、星のボタンでこの記事の感想を教えてください⏬
🔳以下の関連記事もご覧ください
犬と猫のアレルギー性皮膚炎について┃その子に合った治療法を選ぶことが大切
犬・猫のノミ感染を見逃さない!フンの特徴から予防対策まで
犬の皮膚がうろこ状になる理由とは?症状別の受診目安と予防法
ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院
03-3926-9911