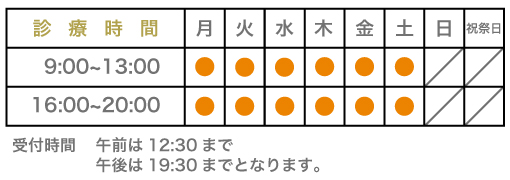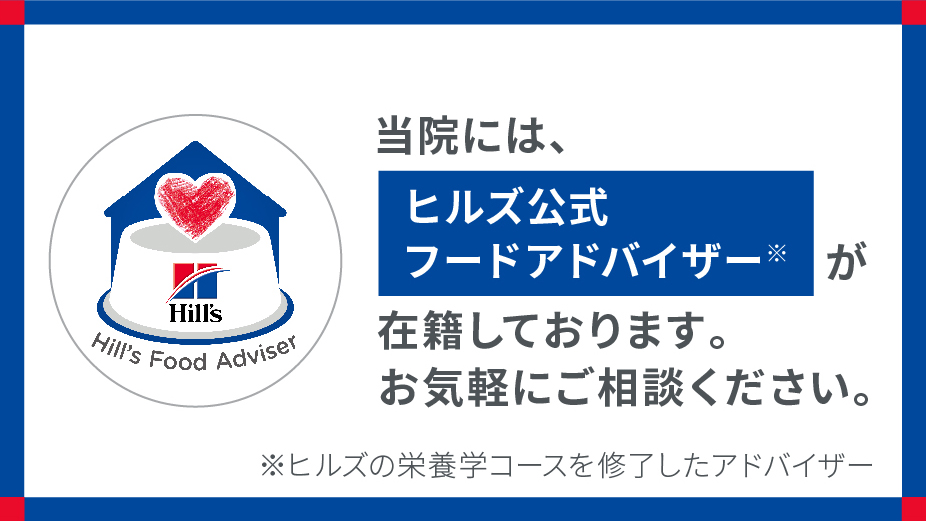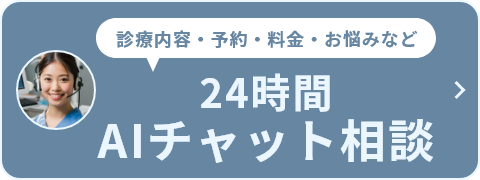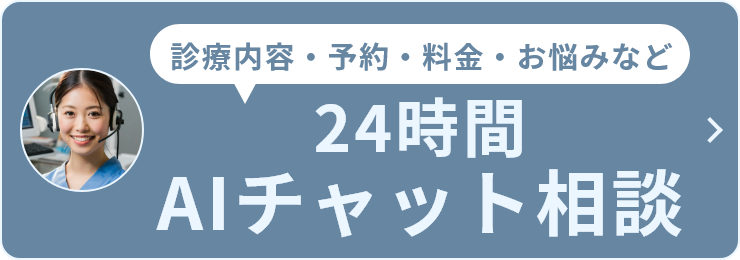犬の脾臓に腫瘍が見つかったら|摘出手術の必要性とその後のケア
脾臓(ひぞう)は、犬のお腹の中にある臓器のひとつで、高齢になると腫瘍が見つかることが珍しくありません。
特に脾臓は血液を多く含む臓器のため、腫瘍が破裂すると大量出血を起こし、命に関わるケースも少なくありません。そのため、状況によっては早めの摘出手術が必要になります。
今回は、脾臓の役割や腫瘍の特徴、摘出手術の流れや術後のケアについてご紹介します。
犬の脾臓とは?腫瘍のリスクと手術の必要性
脾臓(ひぞう)は、胃の近くにある細長い臓器で、免疫や血液に関わる重要な働きを担っています。具体的には、古くなった赤血球の回収や、必要に応じた血液の貯蔵・放出、そして免疫機能の一部も担っています。
この脾臓に腫瘍(しこり)ができることがあり、特に高齢の犬では発見される頻度が高くなります。腫瘍には以下のような種類があります。
・良性腫瘍
ゆっくりと成長し、他の臓器に広がることはありません。ただし、大きくなると破裂するリスクはあります。
・悪性腫瘍(がん)
代表的なものに「血管肉腫」があり、非常に進行が早く、破裂による大量出血や、全身への転移が起こるおそれがあります。
どちらの腫瘍であっても、脾臓が破裂すれば命に関わる緊急事態になるため、腫瘍が見つかった段階で早めの判断が求められます。
<なぜ脾臓摘出がすすめられるのか>
脾臓腫瘍は、ちょっとした衝撃や運動がきっかけで破裂することがあります。悪性の疑いが強い場合はもちろん、良性であっても破裂リスクがある場合には、脾臓摘出手術が選択肢になります。
当院では、腫瘍の種類にかかわらず「破裂リスクが高い」と判断される場合には、早期の摘出手術をおすすめしています。命を守るために、早めの決断が重要になるケースも多いためです。
脾臓腫瘍の診断と摘出手術の流れ
脾臓腫瘍は、早期に見つかれば命を救える可能性が高い病気です。しかし、進行するまで症状が出にくいため、定期的な検査による早期発見がとても大切になります。
<診断の流れ>
脾臓腫瘍の診断には、以下のような検査が行われます。
・超音波検査(エコー)
脾臓の大きさや腫瘍の有無、腹水の有無を確認します。腫瘍の早期発見に有効です。
・レントゲン検査や血液検査
他の臓器への影響や全身状態を把握します。
・必要に応じたCT検査や細胞診
腫瘍の広がり具合や、ほかの病変の確認に役立ちます。
なお、血液検査だけでは腫瘍の有無を判断することは難しいため、エコー検査などの画像診断が特に重要になります。
<手術の流れ>
腫瘍が確認された場合、破裂によるリスクを回避するために、脾臓摘出手術(脾臓全摘)を行います。
1. 術前検査と準備
まずは血液検査や画像検査(エコー・レントゲンなど)を行い、全身の健康状態や腫瘍の位置・大きさを確認します。必要に応じて、事前に輸血の準備を整えることもあります。
2. 全身麻酔と開腹手術
全身麻酔をかけたうえでお腹を切開し、脾臓を外に取り出します。その後、脾臓につながる血管を一つずつ丁寧に処理したうえで切断し、脾臓を摘出します。
3. 出血確認と縫合
摘出後は出血の有無を慎重に確認し、切開部を縫合します。
4. 摘出組織の病理検査
取り出した脾臓は病理検査に提出し、腫瘍の種類(良性か悪性か)やがん細胞の広がりなどを詳しく調べます。
悪性腫瘍だった場合は、術後も継続的な治療や検査が必要になります。特に「血管肉腫」は血管を通じて他の臓器に転移しやすいため、慎重なモニタリングと治療が求められます。
手術後の過ごし方と継続的なケアの大切さ
脾臓の摘出手術を終えた後は、ご家庭でのケアと病院でのフォローが大切になります。ここでは、術後のポイントをご紹介します。
<ご家庭でのケア>
体力の回復と感染予防のために、次のような点に気をつけてあげましょう。
・安静に過ごす
術後しばらくは激しい運動を控え、ゆったりと過ごさせてあげましょう。お散歩も短めにし、様子を見ながら少しずつ元の生活に戻していきます。
・食事管理
消化のよいフードを選び、無理のない範囲でしっかり栄養をとらせましょう。術後の回復をサポートするため、栄養バランスにも気を配ることが大切です。
・傷口のケア
傷口は清潔に保ち、舐めたり引っかいたりしないように注意が必要です。必要に応じてエリザベスカラーなどを使用しましょう。
<病院でのフォローアップ>
特に悪性腫瘍(血管肉腫など)と診断された場合は、摘出後も体内の他の部位への転移に注意が必要です。継続的な検査や抗がん剤治療(化学療法)を行うことで、腫瘍の進行を抑え、愛犬ができるだけ快適に過ごせるようにサポートしていきます。
定期的な通院とモニタリングを通じて、愛犬の体調の変化を早期に発見できるように心がけましょう。
まとめ
脾臓腫瘍は高齢の犬に多く、進行に気づきにくいこともあります。特に腫瘍が破裂すると、大量出血により命に関わる危険があるため、良性・悪性を問わず、早期の摘出手術が勧められるケースもあります。
術後は安静や食事管理に加え、定期的な検査で再発や転移の有無を確認していくことが大切です。愛犬の体調に気になる変化があれば、早めにご相談ください。飼い主様と一緒に、最善の方法を考えていきます。
⏬よろしければ、星のボタンでこの記事の感想を教えてください⏬
🔳以下の関連記事もご覧ください
犬・猫の定期的なエコー検査が必要な理由|獣医師が解説する重要性と頻度
ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院
03-3926-9911
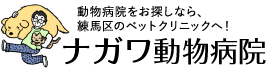


 (8 投票, 平均: 4.13 / 5)
(8 投票, 平均: 4.13 / 5)