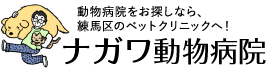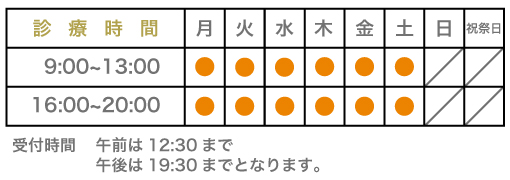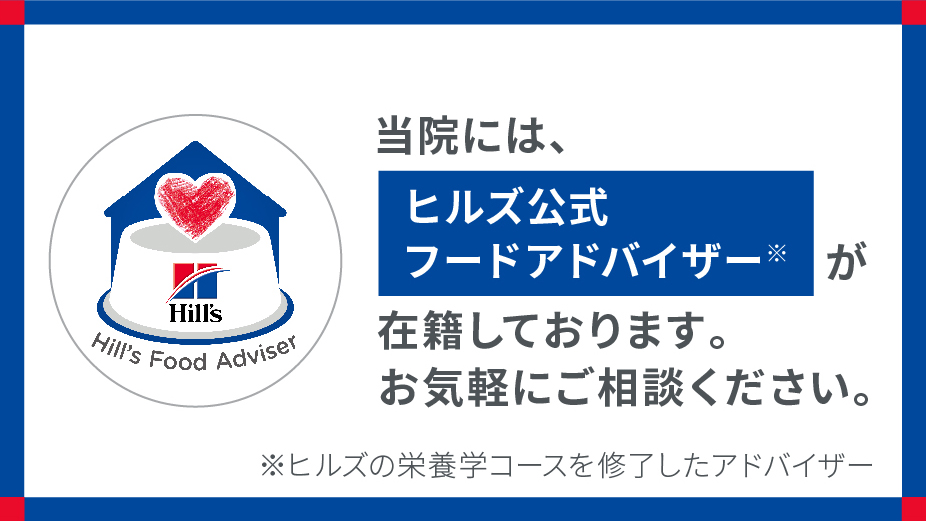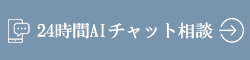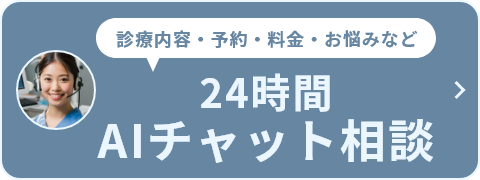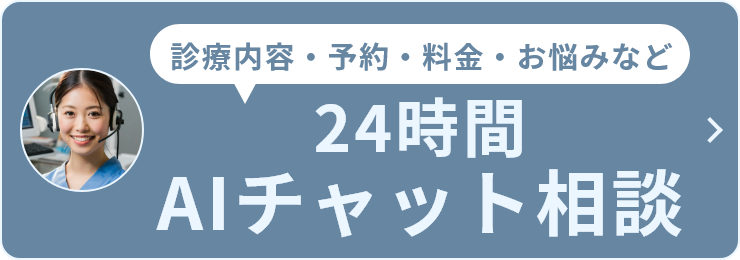動物にはいろいろな悪性腫瘍(がん)が発生しますが、その中でも特に発生率が高いのがリンパ腫です。犬のがんのうち、7~24%を占めるともいわれています。リンパ腫にはいくつかのタイプ(型)があり、それによって治療法も異なるため、正確な診断が重要です。また、リンパ節から他の臓器に転移すると全身に影響を及ぼすので、早期診断と早期治療が必要です。
今回は、犬のリンパ腫に関して、その原因や症状、当院での診断・治療法をお伝えします。
リンパ腫の種類と原因
リンパ腫は、リンパ球という免疫細胞の一種ががん化することで発症します。腫瘍が発生する場所によって、以下のように分類されます。
・多中心型:あごの下、脇の下、内股、膝の裏などに発生
・消化器型:消化管に発生
・縦隔型:胸腔内の縦隔に発生
・その他:皮膚、鼻の中、脾臓などに発生
10歳以上の中高齢犬で多いことが知られていますが、生後半年で発症するケースもあり、若い犬でも油断できません。また、レトリーバー種に好発するといわれていますが、どの犬種でも発症する可能性があります。
症状
初期には目立った症状がみられず、なかなか異変に気付かないこともあります。タイプによって、以下のような特徴的な症状が現れます。
・多中心型
体中のリンパ節が腫れます。特に、あごの下、脇の下、内股、膝の裏などをさわると、固くてゴロゴロとしたものを確認できます。犬のリンパ腫の70~85%ほどを占め、一番多く遭遇します。
・消化器型
見た目には変わった様子がありませんが、下痢や嘔吐といった消化器症状が現れます。慢性腸症などの消化器の病気だと思って受診した結果、リンパ腫と診断されることもあります。
・縦隔型
胸水の貯留や呼吸困難が生じることがあります。
診断
動物病院では、身体検査や血液検査、画像検査(レントゲン、超音波、場合によってはCT)などを実施し、総合的に判断します。
また、生検と細胞診(組織や細胞の一部を採取して顕微鏡で観察する検査)を行い、腫瘍の悪性度や細胞のタイプを確認します。
ステージング(病期分類)
リンパ腫は進行度合いによって、以下のようなステージに分類されます。
ステージ1:1つのリンパ節または組織に限って存在する(骨髄を除く)
ステージ2:所属リンパ節に転移している
ステージ3:全身のリンパ節に転移している
ステージ4:肝臓や脾臓にまで転移している
ステージ5:血液の異変による症状が現れ、他の臓器に転移している
また、サブステージとして以下の基準があります。
A:全身症状なし
B:全身症状あり
ステージが上がるほど予後は悪くなるため、早めの治療が非常に重要です。治療せずにいると、4~6週間ほどで亡くなってしまうことが知られています。また、一般的に、オスよりメス、大型犬より小型犬の方が予後は良いとされています。
治療
リンパ腫は現状の獣医療では根治が不可能です。
治療の目的は良好なQOL(生活の質)を維持することで、少しでも長く元気な状態で生活をしていただくことです。
治療の選択肢には以下のものがあります。
・化学療法(抗がん剤治療)
治療によく反応しますが、再発することが多いです。人間の場合は骨髄移植などで完治を目指せますが、動物では難しいため、これ以上悪化させないことを目標にして実施します。
・免疫療法
当院では、フアイア(TPG-1)という免疫力をサポートする成分を含むサプリメントを活用しています。免疫力を高めることで、がんに対して有効に働くことを示す論文も出ています。
・緩和ケア
痛みやだるさなどの不快感を和らげたり、食事を取りやすくなるようにサポートすることで、QOLを保ちます。
・食事療法
自力で食事をとれない場合、流動食を管(フィーディングチューブ)から摂取させることで、必要な栄養を補給します。この治療に抵抗がある飼い主様もいらっしゃいますが、おなかがすいても食べられないという状況は、犬にとってとても大きなストレスになります。また、しっかりと栄養補給することで、抗がん剤の副作用を軽減することもできるので、当院では必要があれば実施をお勧めしています。
・放射線療法
全身麻酔が必要なので、何度も実施するのはあまり現実的ではありません。
・外科的治療(手術)
QOLを著しく低下させる場所に腫瘍ができた場合に検討しますが、根治につながるわけではありません。
ご家庭での注意点
リンパ腫は再発する可能性が高いため、治療中は愛犬の様子をよく観察し、異変があればすぐに動物病院を受診しましょう。
抗がん剤の使用により副作用が現れることもあります。下痢や嘔吐は数日で治まることが多いですが、長く続く場合は獣医師に相談してください。また、排せつ物には抗がん剤の成分が残っている可能性があるため、取り扱いには十分注意しましょう。
まとめ
リンパ腫は犬に多いがんの一つです。愛犬と長く健やかに過ごすためには、早期発見・早期治療がカギとなります。そのためには定期的に健康診断を受け、日常生活ではわからない異変も見逃さないようにしましょう。治療は長期にわたることが多いですが、抗がん剤、食事療法、免疫療法などを組み合わせることで、より長くQOLを維持して愛犬との生活を楽しむことができます。
ペットクリニックを練馬区でお探しならナガワ動物病院
03-3926-9911
<参考文献>
Bite-size introduction to canine hematologic malignancies – PMC (nih.gov)